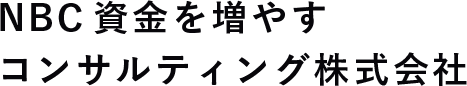~翌月1日に瞬間くんを出す為に~
私のご支援先様のお話をしたいと思います。
先日、8月31日に指導でお伺いした時の話です。
結論から申し上げますと、
「その日に8月分の必要数値を把握し瞬間くんに入力」してもらい、資金分析を実施する事が出来ました。
そのご支援先様は建設業(電気工事業)で規模7千万程です。
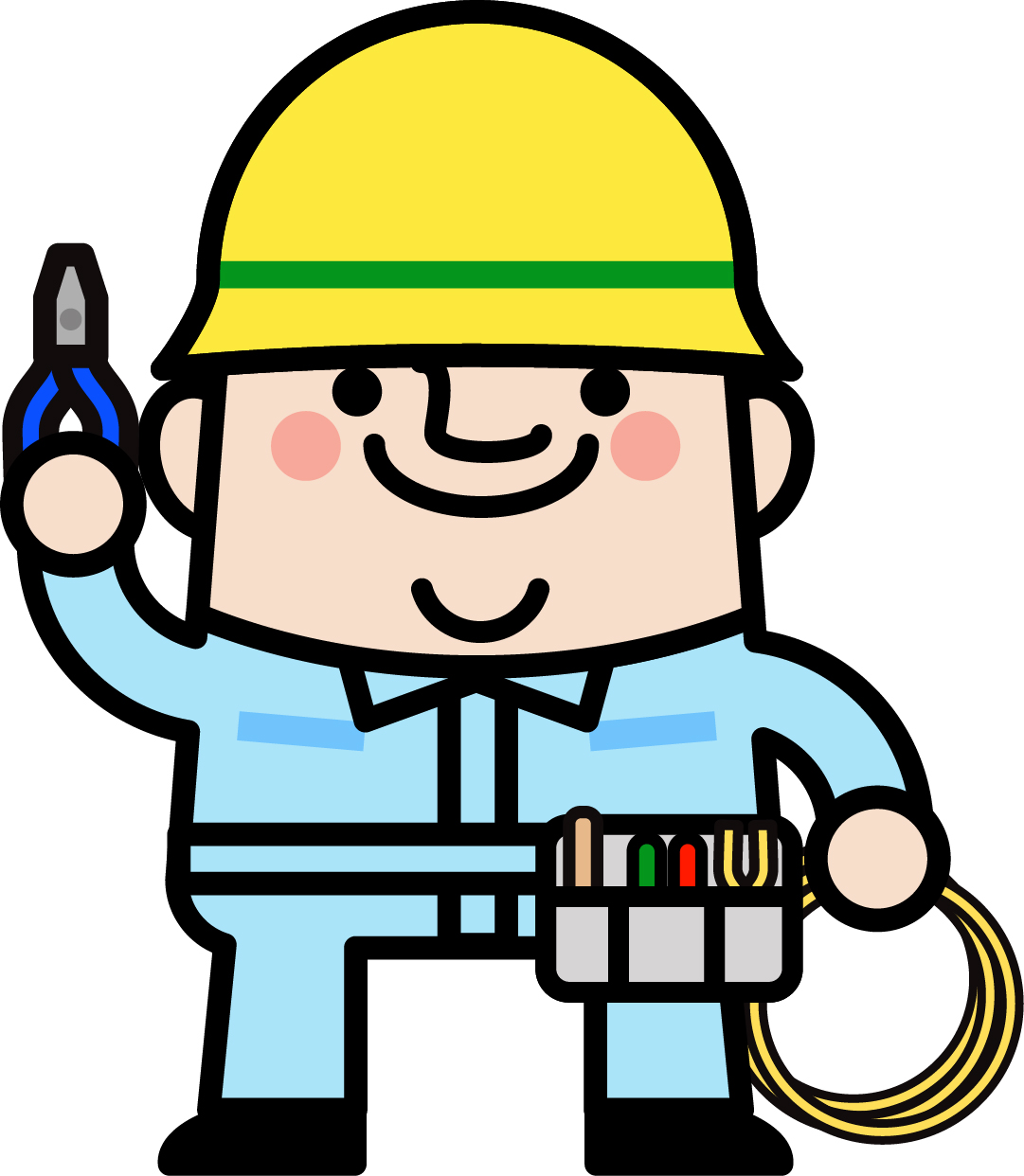
どのように数値を把握し、入力を進めていったのか、その流れを簡単にご紹介します。
まず、瞬間くんで資金分析を実施する為に必要な項目は主に下記6点です。
※業種により名称や必要項目は若干変動します。
【必要項目】
① 現金及び預金
② 借入金
③ 売掛金
④ 在庫
⑤ 買掛金
⑥ 未払費用
① 現金及び預金は日々会計データへ入力
⇒瞬間くん入力の上で最も重要なポイントが現預金、そして借入金です。
自己資金の算式ですね。ここがぶれてしまうと全てが狂ってしまいますので要注意です。
現金は弥生会計へ直接入力し会計データを現金出納帳として機能させています。
預金は当座預金と普通預金があり、当座預金は当座勘定照合表、普通預金はインターネットバンキングから明細を出力して頂く事でタイムリーに数値を把握出来ます。
それらを弥生会計へ入力し、残高を把握していきます。
② 借入金
⇒①を実施する事で借入金は自動的に把握する事が出来ます。
若しくは金融機関毎に借入返済予定表があるのでそれを用いて把握する事も可能です。
③ 売掛金
⇒現場完了後、請求書作成を即座に実施していますのでそれにより毎月計上する合計額は把握できます。後は①を実施する事により売掛金の回収は把握出来ますので、売掛金残高は分かるようになります。
④ 在庫
⇒建設業(電気工事業)という業種上、そもそも在庫が少なく、毎月の変動もありません。
そこで、在庫は動きが無い場合は前月末と同額を計上し、現場の状況次第で在庫の動きが多く明らかに変動している場合は実地棚卸を月末で実施するという事で決定しました。
⑤ 買掛金
⇒主に原価(材料仕入や外注)に対する請求額の残高把握が必要です。
瞬間くんシステムを活用頂いている多くの企業様で悩まれるケースとして多いのは、
下記のような場合ではないでしょうか。
「請求書が到着してからしか数値把握が出来ない為、瞬間くん入力が遅れてしまう」
「先方都合でそもそも請求書の到着が遅い」
実は、ここも解消法があります。
結論としては、「発注段階で金額を把握し請求書が届く前に残高を把握してしまう」です。
材料仕入や外注に対する請求書が届いてからでは遅い、しかしこの支払に対しては自社で発注を行っているという事実があります。ですので、発注⇒納品⇒請求という流れが本来の流れになります。建設業(電気工事業)では発注後に納品書が随時届く流れになっていますので、それを都度計上しておき、月末時点で当月請求金額を積み上げる事が出来ていたのです。これが非常に重要なポイントです。
※企業様によっては発注する際に稟議を設けている場合もあります。
⑥ 未払費用
⇒主に一般経費関連の請求額の残高把握が必要です。
ここは⑤の買掛金残高と同様のイメージです。
こちらのご支援先様ではカード使用による現場経費、旅費交通費、ガソリン代や定期契約している一般経費関連を未払費用として計上しています。
カード関連は使用時にレシートを必ずもらうようにし、その都度計上する事でクレジット使用明細が来る前に把握し(最近はクレジット会社のサイトで使用分はある程度タイムリーに出るようになっていますのでそれで把握する事も可能です)、定期契約している一般経費は解約しない限り毎月同額計上すれば数値を把握する事は容易です。
このようにして、①~⑥までの数値を早期に把握出来る体制を作り上げ、見事に冒頭申し上げたように月末時点で瞬間くん入力を実施頂けました。
因みにですが、こちらのご支援先様は当初「年に1回、決算時にしか試算表を作成」していない企業様でした。それが約2ヶ月という短期間でタイムリーに数値を把握出来る所まで前進する事が出来ました。
我々の資金を軸にした経営の考え方、その為に数値を早期に出すという事の必要性に共感頂き、社長ご自身で強く推し進めてもらっているという点が大きな要因です。
全て社長のご決断、そしてスピード感ある行動力によるものです。
瞬間くんが翌月1日に出ないと悩まれている企業様のヒントになれば幸いです。
鈴木
| ↓↓↓書籍のご購入はこちら↓↓↓ |
 |
| ↑↑↑書籍のご購入はこちら↑↑↑ |